ざっくりとしたMeta Quest 2へたどり着くまでのVRゴーグルの歴史
まずは、Meta Quest 2にたどり着くまでのOculus (現在:Meta)進化の歴史をざっくりおさらいしたい。
2012年:クラウドファンディング発の安価なVRヘッドセット Oculus DK1/DK2 の登場(開発者向け)
人間に立体的な映像を見せるには、左右の眼に対して異なる映像を見せる必要がある。
また、VRゴーグルという限られた空間の中で視界いっぱいに広がる没入感のある大きな映像をどう映し出すのか、実現することが技術的・コスト的に難しかった。例えば、画面をレンズで拡大しようとすると見える映像は歪んでしまうからだ。
小型プロジェクタを内蔵し、投影された映像をみるなどのアプローチも取られたが、大きい・価格が高いで現実的ではなかった。光源は内蔵できず、外部から光ファイバーで供給している。
しかし、Oculusは安価にVRゴーグルを作ることに成功した。
レンズのゆがみに合わせて映像をあらかじめ歪ませるという逆転の発想をした。
これによって、画面にも特殊な加工が必要ないので、すでに流通していて安価に入手できたスマホの画面をそのまま流用すればよい。両目別々で画面を用意することなく、1枚の画面の中間に仕切りを作ることで、両眼分の映像を映せるようにした。
当時のOculusは、上下の傾き、左右の首振り、時計回り/反時計回りの回転の3軸自由度(3DoF)のみの動きに対応しており、人間が動き回ることでVR空間を自由に動き回る6軸自由度(6DoF)には対応していなかった。
センサーとしてはジャイロセンサーのみ搭載されていた。動作には別途ハイスペックPCが必要であった。
2014年:ベンチャー企業のOculus VR社はFacebook社に買収された
Oculus VR社 はFacebook社に20億ドル(約2230億円)で買収された。実は30億ドルだったという話もある。
2016年:初の一般向けOculus Rift (Consumer version, CV1)の登場とOculus Touchコントローラー
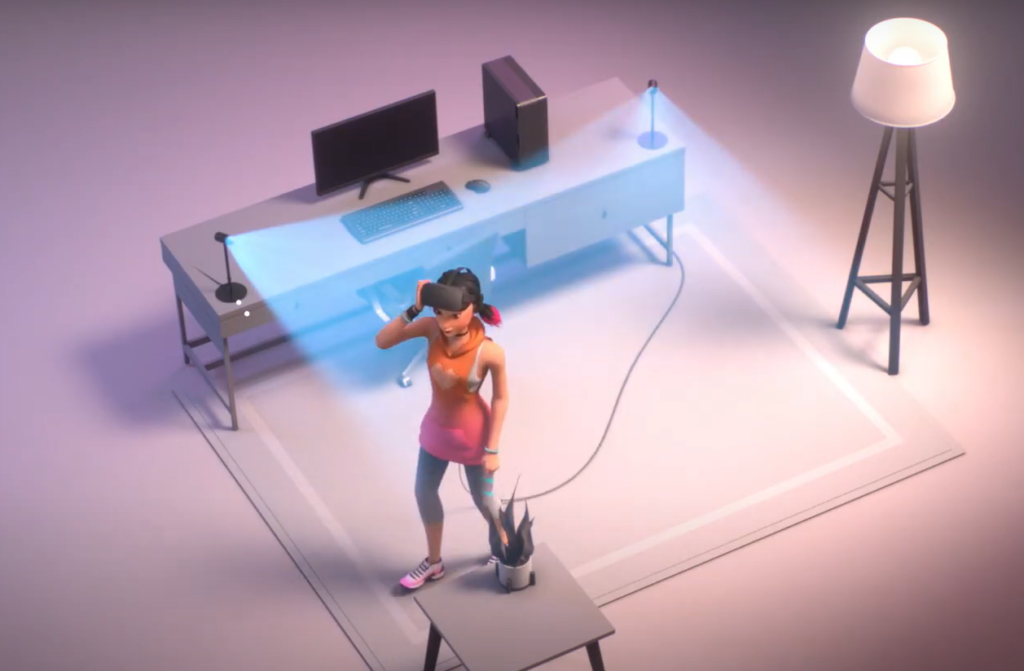
高性能なPCと外部センサーを用いることで、 VR空間を自由に動き回る6軸自由度(6DoF)を実現した。
センサーの設置の必要性やセンサー位置制約による設置の難しさ、精度向上のハードルなどがあった。
高性能なPCが必要なことからコストもかかった。 また、ゴーグルとPC間にケーブルが必要なことから煩わしさがあった。
同時期にOculus Touchがリリースされた。これによって手の動きをVRの中で表現できるようになった。例えば、銃のマガジンを変更するようなアクションや、両手を広げて羽のように空を飛ぶ、モノをつかんで投げるなどの細かい表現が可能になった。
2019年:内蔵カメラで位置トラッキングを行うOculusインサイトを備えた「Oculus Quest」の登場とOculus Link
Oculus Questというスマートフォンのように単体で動作するVRゴーグルが登場した。
Oculusに複数のカメラを内蔵し、この複数の映像とジャイロセンサーの情報から高度な物理予測演算も行うことで、人間の位置(部屋を動き回るとVRの世界でも動ける)やコントローラーの向き・場所をVR世界の中に反映できるようになった。別付けのセンサーなしで 6軸自由度(6DoF) を実現してしまった。これがOculusインサイトである。
動ける範囲の設定は、コントローラーを用いて床に線を引いて行う。壁などに近づくと、VR空間の中でラインが表示され、危険予知ができるようになっている。
もともとは高性能なPCが必要なくらい重い処理が必要なVRゴーグル用の頭脳部(≒PC)を中に入れてしまったのだから、体験できる映像はPC VRと比較すればそこそこだ。
そこで、PCと接続を行い、PCで処理を任せるための接続機能Oculus Linkも備わった。
2020年:Oculus Quest 2の登場
Oculus Questでほぼほぼ形になったスタンドアローン型のVRゴーグルをブラッシュアップしつつ、上手に不要な部分のコストカットを行ったのがQuest 2だ。
初代Questに比べ、映像がより美しく細かく表示できるようになり、小さな文字もきれいに読み取れるようになった。
PC VRにはまだ敵わないが、 性能の底上げも行われ、FPSゲームなども十分に楽しめるようになった。ゲームのアプリケーションの種類も充実してきている。
視野角や解像度も良好で、画面の粗さも気にならない程度となった。画面の精細度合いはおおよそ4K映像相当である。
映像はパラパラ漫画のようにコマで表現されているが、72Hz→90Hz(Hz = 1秒当たりのコマ数)へ対応し、VR酔いの低減や滑らかなVR体験へと繋がった。
2021年:社名をFacebook社はMetaに変更。Oculusブランドは廃止されMetaブランドへ。
Facebook、、ではなく、Metaは本気なようだ。
あらゆる複雑さが解消され、完成したと言えるMeta Quest 2の完成度の高さ
Quest 2の歴史を紹介したが、この歴史こそがMeta Quest 2のレビューそのものだからだ。
まとめつつ、補足も入れると、
- 特別なセンサーが不要で顔に装着するだけで簡単。
- VRゴーグル単体で動き、YoutubeやVR動画視聴、ゲーム、オンラインVR会議などができる。
- VR空間を自由に動き回れる。
- 立体音響で、人の声や動物の鳴き声など距離感や方向を感じられ、そこにある/いると錯覚してしまう。
- 非常に繊細な動きも表現できる手になじむコントローラー。
- 高性能なPCを持っていてかつ、PCでしか体験できないVRアプリなどを使いたい場合のLink機能。
2021年現在、まだまだ頭脳部である半導体チップの性能向上の見込みはあるとの見方が一般的であるので、スタンドアローンで非常に高精細な体験ができるVRゴーグルへ今後もブラッシュアップされていくことは予想できる。
ただし、Quest 2でひとまずVRゴーグルとしては一つのゴールに達したのではと考える。
これで、VRを体験するためのプラットフォームが完成したのだ。
少し時間を巻き戻せば、iPhoneが登場して、次はアプリがどうなるかだ。TwitterやInstagramなどが誕生したように、次は・・・メタバースだ。Meta Quest 2はメタバースへの最も没入感のあるリッチな入口。。。
メタバースで一緒にライブを見るという体験
Quest 2を購入してから、Venuesというアプリ(β版・現在は終了)でライブ映像を知らない人と見るという体験をした。
会場の入り口付近では、遠くからライブの音声が聞こえつつ左右の人から話し声が聞こえてくる。ライブが映し出されているほうへ振り向くと、人は手を振って盛り上がっている。
巨大スクリーンの前に移動する。左右を見渡すと人が居る、ライブを見に来ているかのような一体感のある感覚を得る。
立体音響と緻密に動くハンドジェスチャーによって、そこに人がいるかのような錯覚してしまう。ゴーグルを外すと別の現実に帰ってきたという感覚を得る。
疑似的にここまで人の五感を騙すことができるようになった。
ゲームやライブような娯楽だけではなく、リモートワークで不足しがちなジェスチャーコミュニケーションなどをとることもできる。
ウェルネス用途にも発展できる。病院から出られない場合に人との距離感を感じられ、孤独感を紛らわすことができる。現実世界では手が動かせなかったとしても、脳波コントローラと組み合わせればVR空間の中でなら手を自由に動かせるかもしれない。
VRゲームは運動になる
VRゲームは全身を使って楽しむものも多く、運動にもなる。程よく動く有酸素運動だ。
Quest2ではゲームで消費した運動量を記録してくれる機能もある。
Apple Watchを装着しているとエクササイズリングがみるみる達成されていくのも面白いし、ゲームで運動になるのもうれしい。
メタバースの始まりに、あなたも参加してみませんか?
まだまだMeta Quest2で動くキラーアプリケーションは存在しない。しかし、これからはじまる時代を感じられるのは確かだ。
じわじわどブロックチェーンをベースとしたゲームが盛り上がりを見せているが、VRとの融合が来る日が待ち遠しい。
オプションで購入できるストラップやバッテリーもあるが、ひとまず筆者は本体だけの購入で満足できた。
よって、オプションの購入は焦らなくてもよいのではと考える。容量に関しては、どれだけアプリをインストールするかを考える必要があるが、筆者は128GBで事足りている。
Meta Quest 2 : 128 GB (定価:37,180円)

Meta Quest 2:256GB (定価:49,280円)

Oculus Linkケーブル

